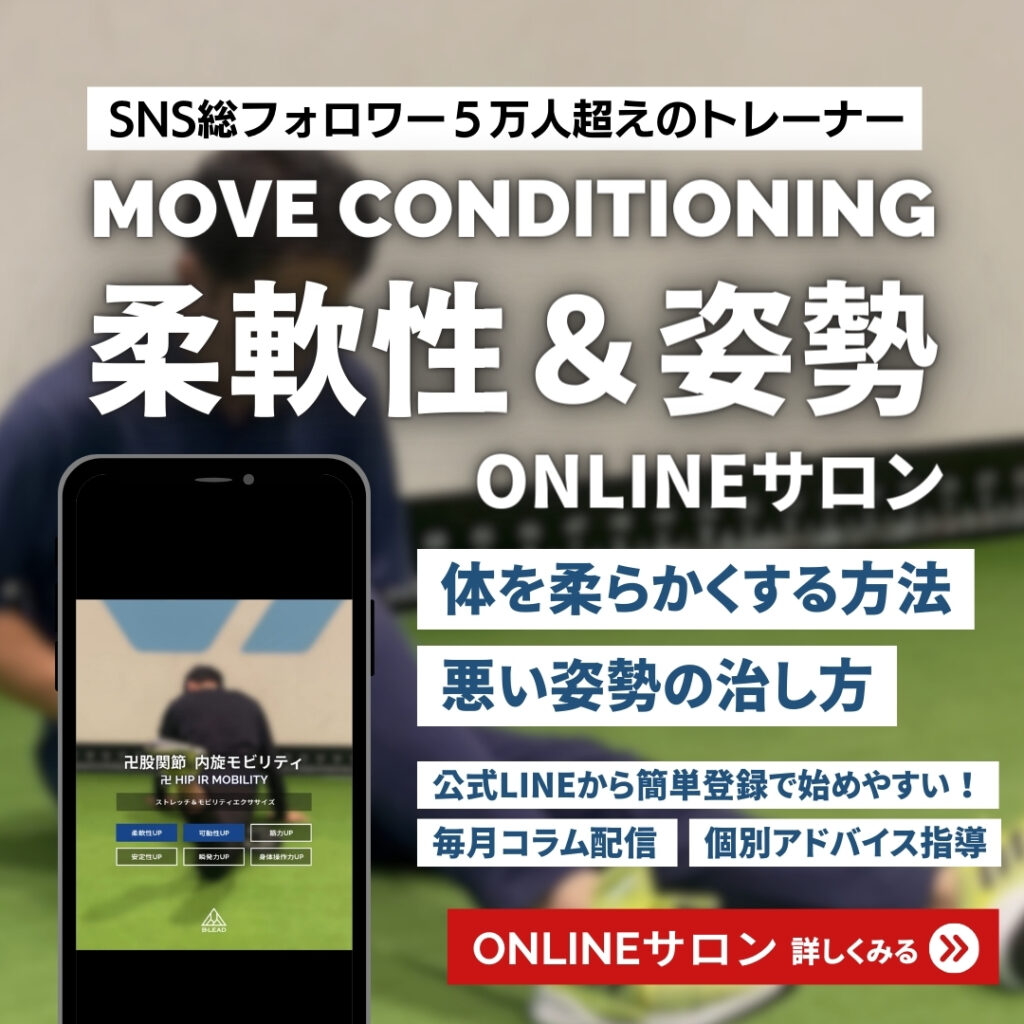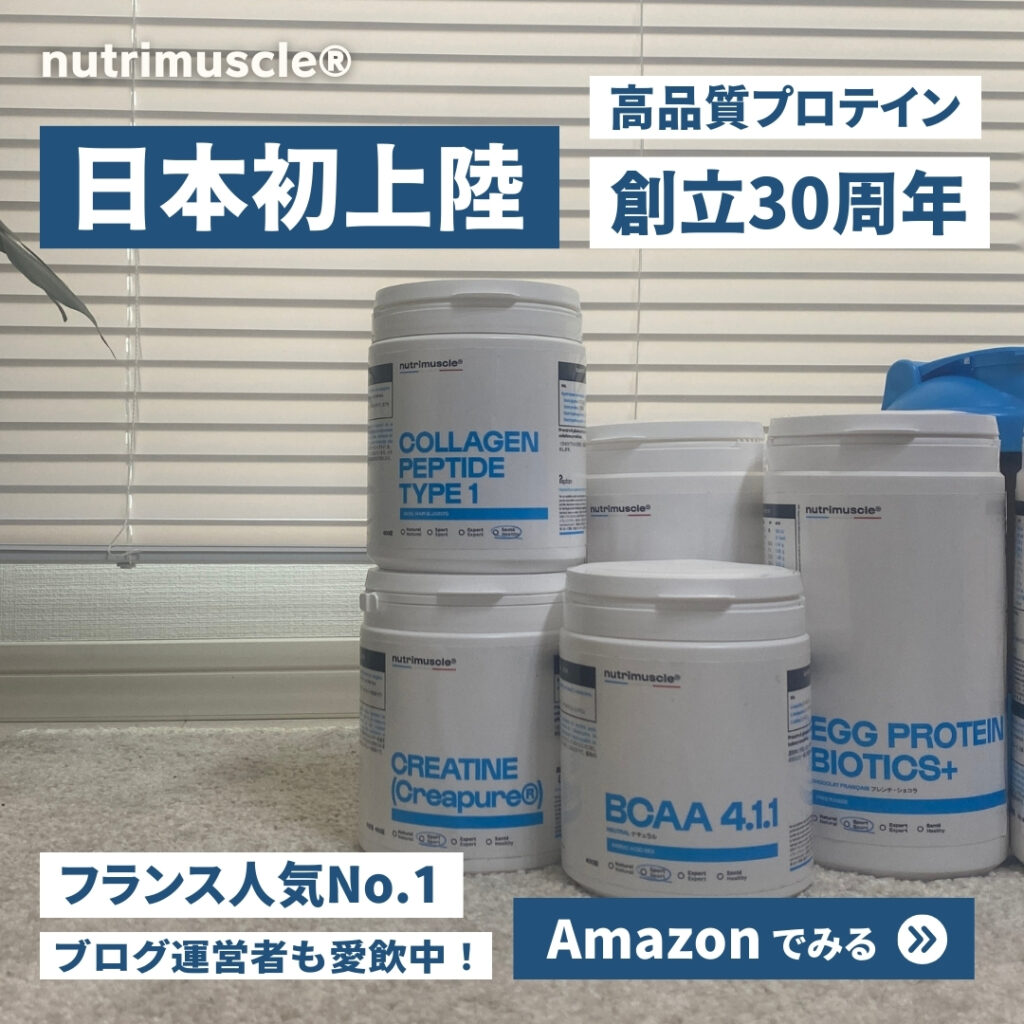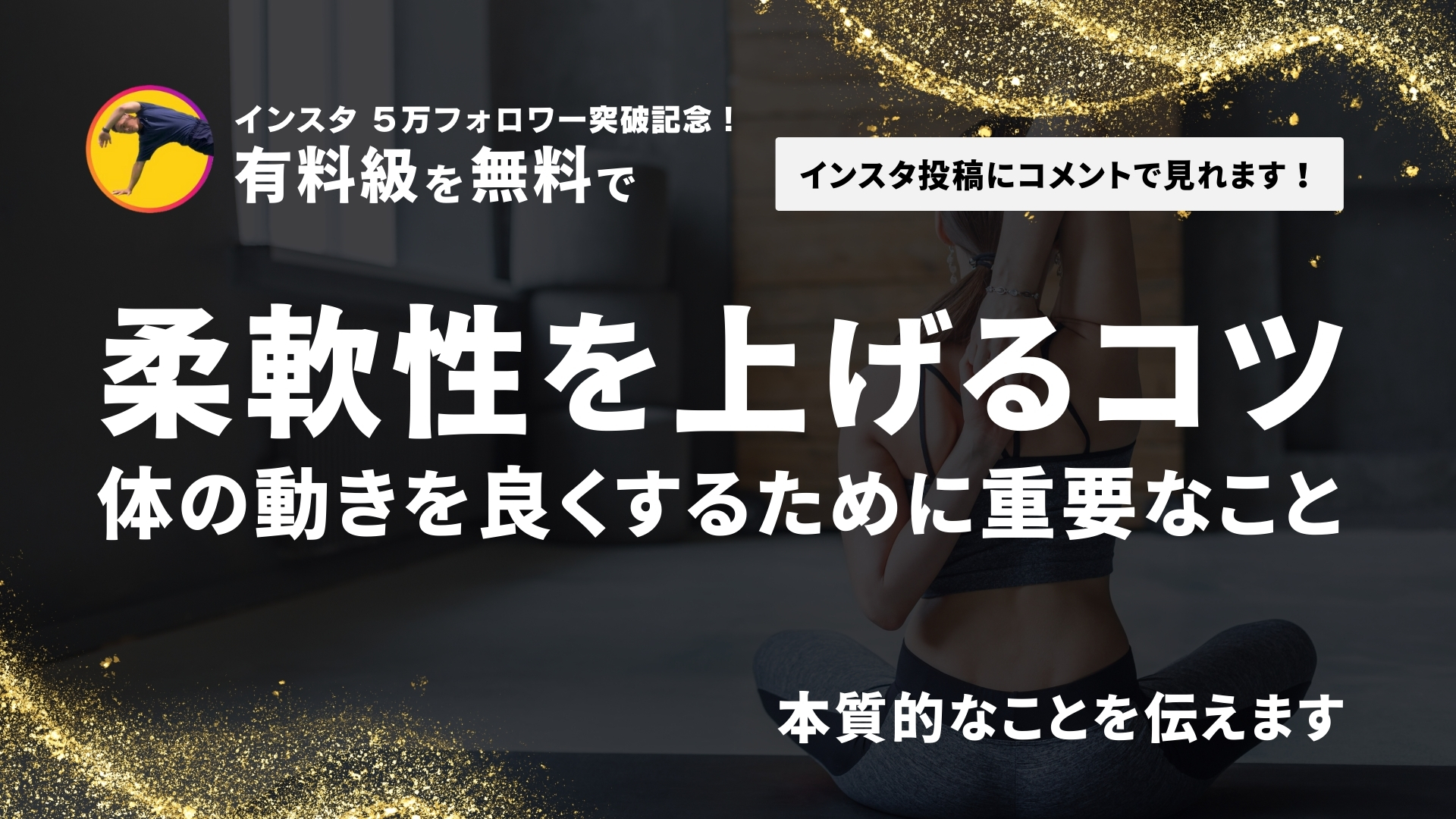【 デッドリフト 】デッドリフトでよく起こる5つの間違い・エラー動作

[chat face=”1.jpg” name=”BODY PARTNARS代表 藤元 大詩” align=”left” border=”gray” bg=”none” style=”maru” ] 大阪を拠点に関西各地方にフリーランスパーソナルトレーナー/アスレティックトレーナー として活動している BODY PARTNARS の 藤元大詩(ふじもとたいし)です!(@taishi_fujimoto) [/chat]
いつもHP&ブログをご覧頂きましてありがとうございます!今回の記事では、デッドリフトとルーマニアンデッドリフトでよくある間違い?エラー動作について解説したいと思います。
デッドリフトのポイントについては、以前にお伝えしたいますのでこちらよりチェックしてみて下さいね!
[chat face=”1.jpg” name=”BODY PARTNARS代表 藤元 大詩” align=”left” border=”gray” bg=”none” style=”maru” ] 競技力向上や傷害予防に対して取り組んでいく上で実践されることが多い種目の一つです。実践する目的によってさまざまな効果が期待できます。
正しいフォームを習得して実践・継続することが大前提です。
エラー動作で継続していくと逆効果というか、身体を痛めてしまう原因に繋がってしまます。パフォーマンスも低下してしまいます。。 [/chat]
そもそもデッドリフトやルーマニアンデッドの違いについて知っている人も少ないかもしれません。。それらの違いを踏まえてお伝えしたいと思います。是非最後までご覧下さいね!
デッドリフトでよく起こるエラー動作

[chat face=”1.jpg” name=”BODY PARTNARS代表 藤元 大詩” align=”left” border=”gray” bg=”none” style=”maru” ] デッドリフトやルーマニアンデッドリフトでよくありがちなエラー動作・パターンについては以下の通りです。 [/chat]
- 腰や背中が丸くなる(腰椎の彎曲減少)
- 腕に力が入り過ぎている
- バーが身体から離れ過ぎている
- 踵重心(足底重心の後方移動)
- アゴが上がっている(頸椎の過度な伸展)
ザックリとこのようなエラー動作・パターンが考えられます。また、これらのエラー動作が起こってしまうことにはさまざまな原因が考えられます。
ひとつひとつ詳しく解説したいと思います。
①腰や背中が丸くなる(腰椎の彎曲減少)
恐らくですがデッドリフトで一番多い?エラー動作として「腰や背中が丸くなる」ことがよく起こります。
腰が丸くなるということは、生理的な彎曲である腰椎の前弯が減少することを意味しています。多くの一般の人・スポーツ選手はある程度、腰が丸くなっても動作を続けます。そして、腰痛などの痛みが発症してから気づくことが多いです。
考え方によっては「痛みは悪い動作を知るチャンス」でもあります。
[jin-iconbox06]このような腰・背中が過度に丸くなった、腰椎の彎曲が減少した状態では、椎間板・椎間関節に過度なストレスを与える原因です。[/jin-iconbox06]
このようなストレスが加わった状態で動作を繰り返すと場合によっては、腰椎椎間板ヘルニアを発症することにも繋がっていまします。。
[jin-iconbox07]腰が丸くなってしまう原因には、動作時の股関節の動作不良や股関節の柔軟性・可動性の不足、体幹部の安定性不足、脊柱の軸伸展の減少などが考えられます。
あとは、単純に重量が過負荷すぎる状態なども考えられます。[/jin-iconbox07]
一人一人、腰が丸くなってしまう原因は違ってくるはずなので原因に合わせて改善していくようにしていきましょう。
②腕に力が入り過ぎている
腕に力が入り過ぎることも多いです。
腕に力が入り過ぎると…本来の目的としている効果を最大限に引き出すことが難しくなってきます。デッドリフトでは、バーを持った状態で実践していきますが腕を鍛える種目ではありません。
メインに使う部位は主に下半身や背面の筋群です。
[jin-iconbox01]腕に力が入った状態、入りやすい状態で続けているとセットの後半になった時に握力がもたなくなってしまいます。[/jin-iconbox01]
まずは、単純に腕をリラックスした状態を維持できるように意識を繰り返していきましょう。その人にとって重量が重すぎることも力が入り過ぎてしまうことに繋がってしまいます。
[jin-iconbox07]腕に力が入りすぎる原因には、肩関節が安定していないことも一つの原因として考えられます。肩関節が正常に求心位を取れていることが大切。
バーを握った状態でも軽く肩甲骨を寄せるイメージを持ったり、回旋筋腱板が機能している状態を作ることもポイントです。[/jin-iconbox07]
③バーが身体から離れ過ぎている
これは、デッドリフトやルーマニアンデッドリフトを実践する上で基礎的なフォームです。バー(シャフト)は、なるべく身体の近くを通すイメージを持つことが大切。
最初は、下腿部(スネ)の前方、次にひざ・大腿部の前方の近くを通過するように持ち上げていきます。
[jin-iconbox01]バーが身体から離れ過ぎていると肩や首周辺が疲れちゃいます。[/jin-iconbox01]
バーが離れると不安定になるので、動作時もしっかりと身体に引き寄せた状態をキープして力強く持ち上げていきましょう。
④踵重心(足底重心の後方移動)
動作時に踵重心になってしまっているケースも多い例です。
デッドリフトでは、股関節の屈曲動作(ヒップヒンジ)が強調されるトレーニングのため、お尻を後方に引くという動きが行われます。その動きと同時に重心も後方へと移動する人が多いです。
踵重心の癖がついてしまうと競技者では、パフォーマンスの低下や特定の外傷・障害のリスクにもなっていきます。
[jin-iconbox07]ヒップヒンジの動作時にも足裏全体で支える状態が理想的です。[/jin-iconbox07]
この動作は多くの場合、正しいフォームへと改善するような指導をしていくことで修正していくことができます。まずは、バーベルなしの状態で正しい動作・重心の位置が保てるか実践・練習していきましょう。
⑤アゴが上がっている(頸椎の過度な伸展)
デッドリフトやルーマニアンデッドリフト時にアゴが上がっている多いケースです。
アゴが上がっている状態では、頸椎が過度に伸展している状態になっています。頸椎が過度に伸展した状態で重量を持ち上げると呼吸補助筋が活動を起こして本来機能すべき、体幹の筋群が働きにくくなっていきます。
体幹筋群の出力が低下してしまうと腰部が不安定になる可能性が考えられます。
[box04 title=”呼吸補助筋”]「胸鎖乳突筋」や「斜角筋」などの筋
これらの筋は、頸から鎖骨・肋骨にかけて付着する筋です。過度に活動することが原因となって肋骨が開いてしまうことに繋がってしまいます。[/box04]
[chat face=”1.jpg” name=”BODY PARTNARS代表 藤元 大詩” align=”left” border=”gray” bg=”none” style=”maru” ] 鏡を前にすると、どうしてもフォームを確認することに集中して前を向いてしまいます。アゴが上がる原因です。
身体の構造解剖学から考えていくと、基本はアゴを引いた状態が理想的です。
アゴが上がった状態で実践していくケースもあります。例えば、トレーニング上級者の方で高重量を扱う場合にアゴが上がっているケース。この場合には、体幹筋群もきちんと機能した状態で実践することが求められます。 [/chat]
デッドリフトやルーマニアンデッドリフトで体幹筋群の機能が働いていない状態では、腰痛の原因に繋がります。
デッドリフトとルーマニアンデッドリフトの違いとは?
デッドリフト(DL)とルーマニアンデッドリフト(RDL)の違いについて解説したいと思います。皆さんは知っているでしょうか??
意外にも違いについて知らない人は多いんじゃないかと思います。
[box04 title=”デッドリフト(DL)とは?”]大腿四頭筋や脊柱起立筋群、ハムストリングス、大臀筋を中心とした下半身全体を使う種目。
スクワットのように下半身を動かしながらバーベルを下から引き上げていきます。膝関節ちお足関節の屈曲角度が大きくなります。[/box04]
[box04 title=”ルーマニアンデッドリフト(RDL)とは?”]ハムストリングスや大臀筋、脊柱起立筋群を使う種目。
股関節中心の動きで足関節は安定させた状態で膝の位置も変わらない状態で実践していきます。通常のデッドリフトと同じくバーベルは下から引き上げる動作で行っていきます。[/box04]
違いについて少しはイメージ・理解できたでしょうか??参考までに動画もご覧下さい。
デッドリフト(DL)の実践動画
ルーマニアンデッドリフト(RDL)の実践動画
[chat face=”1.jpg” name=”BODY PARTNARS代表 藤元 大詩” align=”left” border=”gray” bg=”none” style=”maru” ] 選手や一般の方の競技力向上や傷害予防、機能改善をしていく中では、ルーマニアンデッドリフトを推奨しています。
目的によって使い分けが大切ですが通常のデッドリフトであれば、スクワットのバリエーションを加えて指導することが多いです。RDLでは、股関節のヒップヒンジの動作習得が期待できるのでさまざまな目的にフィットさせることができます。 [/chat]
※デッドリフトが悪い種目という訳ではありません。トレーニングも目的によって優先順位が異なってくるので目的・種目の優先順位によっては取り入れても良いと思います。
この記事のまとめ&最後に

デッドリフトやルーマニアンデッドリフトでよく起こる間違い・エラー動作を少しでも知ることができたでしょうか??
エラー動作で続けていても目的に対して期待している効果どころか、場合によってはケガを引き起こしてしまうことも考えられます。
上記2つの種目は、正しい動作・フォームで実践することで非常に良いメリットを得られることが期待できます。正しい動作を意識しながら目的を持って取り組んでみて下さい!
それではまた次回の記事&YouTubeでお会いしましょう!